
こんにちは。【ADHD夫を支える妻】はっさくです。
先日に引き続き、息子の発達相談での学びをシェアします。
先日は「恐怖心の強い子どもへの声かけの工夫」を紹介しました↓
今日も引き続き、恐怖についてお話しします。
発達障害の特性やHSC気質のある子どもの中には、人一倍強い恐怖心から小さなことでパニックを起こす子どもがいます。
息子もその1人で、日常の何気ない場面で大パニックを起こすことがあり、対応に困っています(息子の様子はこちら)。
今日は、発達相談で教わった【特性のある子どもの恐怖やパニックを和らげる方法】を紹介します。
※発達相談での学びをゆるっとまとめています↓
- 発達相談①:「お子さんはコミュニケーションの障害がある」と言われた
- 発達相談②:子どもの恐怖に「大丈夫」は逆効果!?
- 発達相談④:小さなすり傷でパニックに!?どう対処する? - グレーゾーンなわたしたち
恐怖は「克服するもの」ではなく「緩和するもの」
「息子の恐怖心を克服するための手立てはありますか?」
そう聞いたところ、臨床心理士さんはこんなことを言いました。
「お母さん、恐怖は『克服するもの』ではなく『緩和するもの』ですよ」
なるほど。
人一倍怖がりで小さなことで大パニックを起こしてしまう息子。

何でこんな小さなことで?うちの子大丈夫かな・・・
そんなことをつい思ってしまいがち。
事実、極端な恐怖心は集団生活の妨げになるだけでなく、新しいことへ挑戦したい気持ちを阻む原因にもなります。
だからといって、怖がる子どもに「怖がるな」というのは到底無理な話です。
目標にすべきは「恐怖そのものの克服」ではありません。
恐怖があってもそれを「うまくやり逃す」「和らげる」。
その方法を一緒に模索することが何よりも大切です。
「怖い」という感じ方そのものを変えることは難しくても、具体的な手立てをもってすれば恐怖を和らげることは可能です。

恐怖の背景を分析する
恐怖を和らげるためにはまず、恐怖の背景を分析する必要があります。
漠然とした恐怖ほど怖いものはありません。
恐怖を分析することで、それを「うまくやり逃す」「和らげる」ための対策が立てやすくなります。
特性のある子どもの強い恐怖の背景には、例えば以下のようなものがあります。
①感覚過敏
感覚過敏とは、脳や感覚器の機能不全が起こっている状態のことです。
刺激への過敏さが強い恐怖の原因となる可能性があります。
息子のように人一倍耳や鼻が敏感である子どもにとっては、感覚刺激からくる恐怖は相当なものであると考えられます。

※「感覚過敏」について詳しく↓
②認知の歪み
認知の歪みとは、ある出来事に対して事実とは歪んだ極端な捉え方をしてしまうことをいいます。
HSC気質や発達障害のある子どもは、感覚の過敏さに加え認知の歪みが強いことがあり、そのことが恐怖を倍増させている可能性があります。
このように極端な白黒思考や思い込みが恐怖を増幅させてしまいます。
※「認知の歪み」について詳しく↓
その空気、本当に読めている?空気が読めない原因は「認知の歪み」にあった?!
③見通しの悪さ
見通しの悪さは、発達障害(特にASD特性)のある子どもに多いものです。
「見通し」とは、目に見えない不確定の未来のことです。
ASD特性を持つ子どもは、目に見えないものを予測することが苦手です。
恐怖に関していえば、「恐怖が過ぎ去る見通しをうまく立てられないこと」などが恐怖を倍増させる原因になります。

恐怖を和らげる具体的な手立て
恐怖の背景を分析することができたら、それに見合う具体的な手立てを考えます。
ここでは先程紹介した3つの原因(①感覚過敏、②認知の歪み、③見通しの悪さ)からくる恐怖について、それらを和らげる具体的な手立てを紹介します。
①感覚過敏
感覚過敏による恐怖は突然やってきます。
例えば息子は耳がとても敏感で、音に対する恐怖が人一倍強いです。
突然のエンジン音、飛行音、破裂音・・・いつどこで起こるかわからないそれらの音に常にビクビクしています。
「音は突発的にやってくる」
そのことが息子の恐怖をより一層強化しています。

強い刺激が突然くるかもしれないし、怖いかもしれない。
その事実を変えることはできません。
しかし突然の恐怖であっても、とっさにそれを回避することができれば、恐怖を少し和らげることができます。
音のに関していえば、服の袖で耳を塞ぐ、防音イヤーマフをつけるなど、具体物を使って刺激を遮断することで恐怖はかなり和らぎます。
例えば我が家では、防音イヤーマフ代わりにボアのついた耳あてを購入しました。
本格的な防音ではないですが、これだけでかなり音が遮断されます(心理士さんにもボアはオススメされました)。

電車の音が怖い息子ですが、これを持っていけば「ちょっと乗れそうかも!?」とその気になっています。
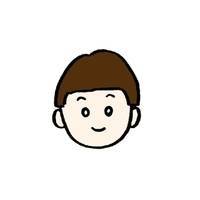
怖い、でもコレがあればちょっと安心☆
そんなアイテムを探すことが大切です。
「怖いけどパニックにならずその場をうまく回避すること」を目標にしましょう。
②認知の歪み
認知の歪みが強い子どもは、恐怖の中身が漠然としてしまいがちです。
思い込みや白黒思考などで恐怖は倍増し、恐怖の根っこが見えなくなってしまうのです。
認知の歪みからくる恐怖を和らげる方法。
それは、「本当に怖いもの」と「怖いものの周辺にある『大丈夫なもの』」を明確に区別していくことです。
こうすることで、本当に怖いものだけを適切に怖がることができるようになります。
認知の歪みが強い子どもの恐怖を図解すると、こんな感じになります↓

しかし実際はこうです↓

「グレーも全部黒に見えてしまう」
そんな白黒思考をひとつひとつ断ち切っていくのです。
具体的には、「怖い」を限定し「大丈夫」を強調するような声かけを地道に行うことが有効です。
こうした声かけを地道に行うことで、本当に怖いものだけを避けて、大丈夫な世界を広げていくことが可能です。
ちなみに・・・

本当に怖いものは無理に克服する必要はない。避けても大丈夫なんだよ☆
何事も「正しく怖がる」ことが大切です。
③見通しの悪さ
見通しの悪さからくる恐怖は、言葉の通り「恐怖が過ぎ去る見通しをうまく立てられないこと」で起こります。
これを和らげるためには、「予告」と「避難経路の確保」が大切です。
例えば電車の発車音が怖い息子に対しては、こんな予告をします。

今から電車が発車するから大きな音がするよ(予告)。10秒で終わるからイヤーマフで耳を塞ごうね(恐怖を回避する手立て)
恐怖が過ぎ去った後は必ず、「ほら、もう怖くないね」「大丈夫だったね」を強調して伝えます。
また、10カウント法といって、恐怖が10秒で通り過ぎることを具体的に示す方法も有効です。
やり方は簡単で、通り過ぎる恐怖に合わせて、10秒声に出してカウントするだけです。
10秒の長さを適度に広げたり縮めたりして、ここでも「10秒で終わったね」「大丈夫だったね」を強調します。
ここで注意すべきは、「予告は外れることがある」という点です。
未来のことはわからないので、予告してもその通りにいかないことがあります。
そこでパニックに陥らないようにするために、予告とともに避難経路の確保(予告が外れたときの逃げ道をつくる)をしましょう。
先ほどの例でいえば、

耳を塞いでもまだ怖いと感じたら、発車するまで待合室に逃げてもいいよ(避難経路の確保)
↑このような一言を添える、というイメージです。
予告が外れてしまっても、避難経路の確保ができていれば恐怖は一層和らぎます。
まとめ
今日は、【特性のある子どもの恐怖やパニックを和らげる方法】を紹介しました。
怖がる我が子を目の前に、こちらががたくさんの引き出しを持っておくことは本当に大切。
これからも地道にがんばります☆
※発達相談↓
- 発達相談①:「お子さんはコミュニケーションの障害がある」と言われた
- 発達相談②:子どもの恐怖に「大丈夫」は逆効果!?
- 発達相談④:小さなすり傷でパニックに!?どう対処する? - グレーゾーンなわたしたち




